ダイオードとは、「電気を一方向にしか流さない」特別な電子部品です。
身の回りの家電やスマートフォンの中にも、実はたくさん使われています。
この記事では、ダイオードのしくみ・なぜ一方向しか流れないのか・どんな場面で使われているのかを、初心者にもわかりやすく図や例え話で解説します!
ダイオード

ダイオードってなに?
ダイオードとは、電気を一方向にしか通さない部品です。
・一方通行の道
・電気の片道切符
どんなときに使うの?
1.電気の逆流を防ぐ(保護)
例えば電池を逆に入れても壊れないように、「逆流防止の安全弁」として使うことが多いです。
2.交流を直流に変える(整流)
家庭の電気(交流)を、機器の中で使える電気(直流)に変えるときにも大活躍。
⇒これを「整流」といいます。
なぜ一方向にしか流せないの?
ダイオードの正体は「半導体」です。
ダイオードは、「P型半導体」と「N型半導体」をくっつけた部品です。
これを「PN接合」と呼びます。
P型半導体(プラスの性質)
「電子が足りない部分(=正孔/ホール)」が多い、電子が入りやすい
N型半導体(マイナスの性質)
電子がたくさんある、電子が出ていきやすい
電流の「見かけの流れ(プラス→マイナス)」に対し、電子はマイナス(−)側からプラス(+)側へ移動することを踏まえ説明します。
PN接合の例え:りんごの受け渡しゲーム
| 半導体 | 例え | 特性 |
| 🔴 P型半導体 | りんご(電子)を受け取りたい人(カゴを持って待ってる) | 電子が少ない(正孔が多い) |
| 🔵 N型半導体 | りんごをいっぱい持ってる人 | 電子が多い |
順方向(電気が流れる状態)の場合
【接続】
電源の + を P型 に、電源の − を N型 に接続
【実際の電子の動き】
電子(りんご)は −側から出発して、+側に向かって流れる(N型 → P型へ移動)
- N型側の人たちは、電源(−)からどんどん「りんご(電子)」をもらって元気いっぱい。
- りんごを持って、P型側のカゴを持つ人たちに渡していく。
- P型側は「待ってました!」とりんごを受け取り、流れがどんどん続く。
このように、電子は「マイナスからプラス」へ流れていく。
りんごが連続で渡されていく=電流が流れる状態!
逆方向(電気が流れない状態)の場合
【接続】
電源の − を P型 に、電源の + を N型 に接続
【実際の電子の動き】
電子は −側(P型)から出発しようとするが、P型には電子が少ないのでほとんど出られない。
- 今度はP型(りんごを持ってない人たち)に「りんごを出して」と言っても、手元にりんごがない。
- N型の人たちは「こっち来て」と言っても、誰も渡せない。
- だから、りんご(電子)はほとんど動かない。
電子が動けない=電流が流れない!
まとめ
| 項目 | 内容 |
| 電子の本当の動き | マイナス(−)→ プラス(+) |
| 見かけの電流(正孔の流れ) | プラス(+)→ マイナス(−) |
| たとえの「りんご」 | 電子のイメージ |
| 順方向で流れる理由 | 電子がN型→P型へスムーズに移動できるから |
ダイオードの見た目
小さな黒い筒に銀や黒の線がついているような形が多いです。
その銀(黒)線が「電気が流れない向き(マイナス側)」を表しています。
まとめ
| ポイント | 内容 |
| 働き | 電気を一方向にだけ通す |
| 例え | 一方通行、逆流防止弁、片道切符 |
| 主な用途 | 逆流防止、整流(AC→DC変換)、保護回路など |
| 関連部品 | LED(発光ダイオード)も同じ仕組み+光る |
おまけ
LED(発光ダイオード)は、電気を一方向に流すと光る特別なダイオードです。
おわりに
ダイオードはシンプルに見えて、実は電子回路に欠かせない縁の下の力持ちです。
一方向にしか電流を通さないという特徴を活かし、整流、保護、点灯制御など、様々なシーンで活躍しています。
この記事を通して、ダイオードへの理解が少しでも深まれば幸いです。次はLEDやツェナーダイオードなど、仲間の部品にもぜひ注目してみてください!
でわっ!!
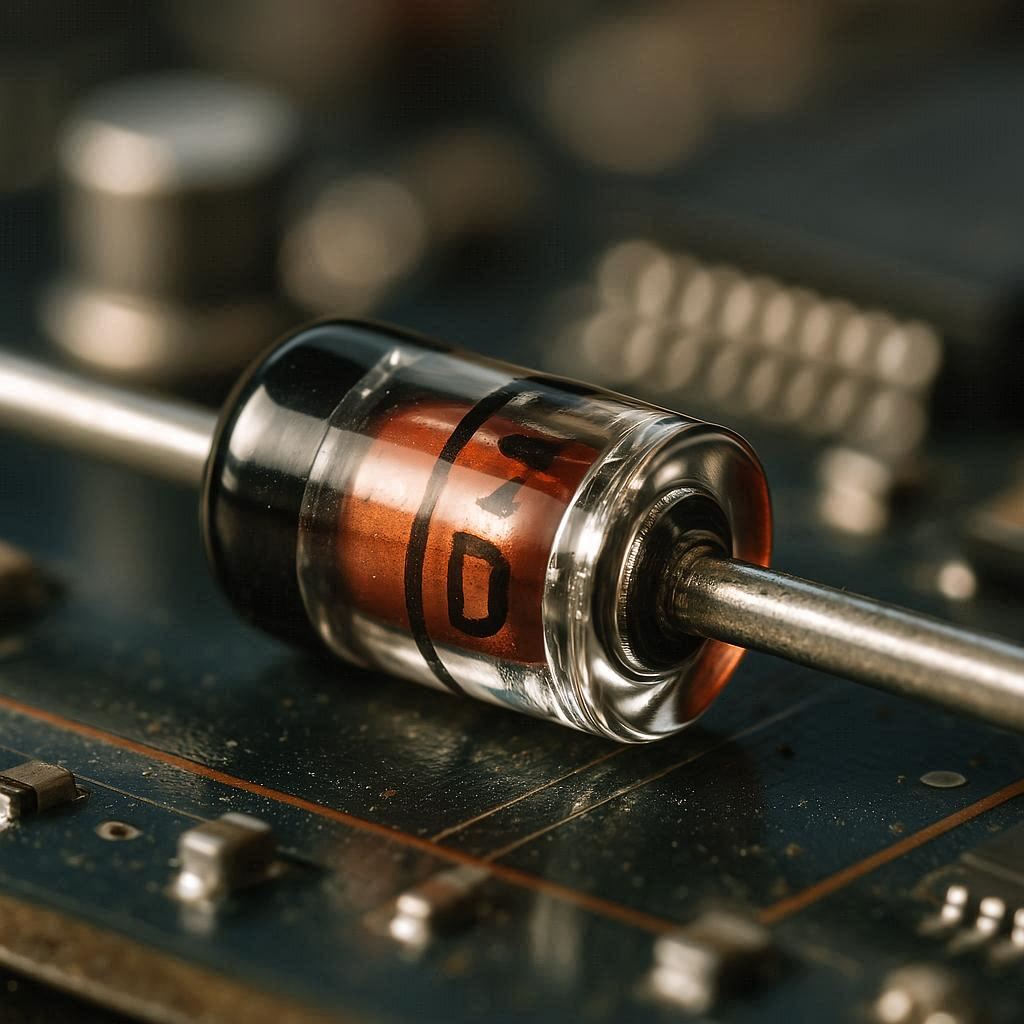


コメント